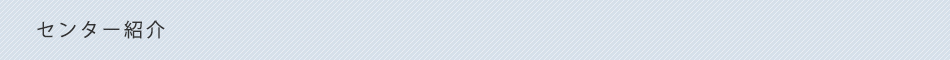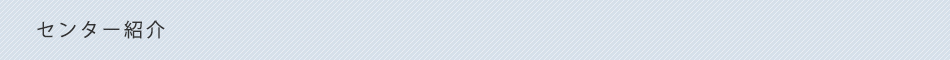歴代センター長・副センター長
2011年4月〜2013年3月 姜尚中(センター長)、木宮正史(副センター長)
2013年4月〜2018年3月 木宮正史(センター長)、外村大(副センター長)
2018年4月〜2023年3月 外村大(センター長)、木宮正史(副センター長)
2023年4月〜現在 外村大(センター長)、木宮正史・三ツ井崇(副センター長)
歴代教員
生越直樹(東京大学大学院総合文化研究科・教授)
月脚達彦(東京大学大学院総合文化研究科・教授)
有田伸(東京大学社会科学研究所・教授)
長澤裕子(東京大学大学院総合文化研究科・特任准教授)
閔東曄(東京大学大学院総合文化研究科・特任助教)
木宮正史(東京大学大学院総合文化研究科・教授、副センター長)
|